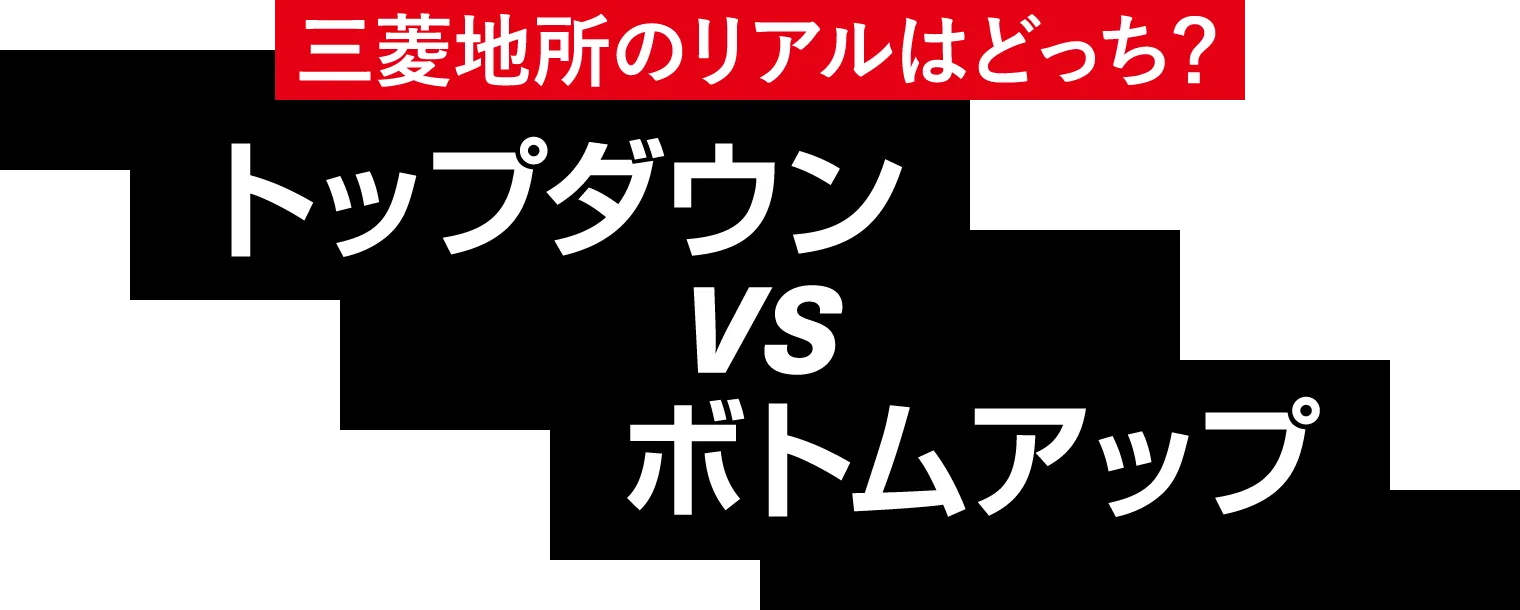INDEX
Introduction
あえて逆の切り口から三菱地所を語ってもらい、リアルに迫る対談。第2弾のテーマは『トップダウンVSボトムアップ』。業界や規模感からトップダウンのイメージをもたれがちな三菱地所ですが、意外と……。キャリア入社の二人がざっくばらんに語ります。
Member Profiles
ディベートメンバー
-

肥爪 聡子(ひづめ さとこ)
2019年入社
海外業務企画部 副主事前職では総合重工メーカーの経営企画・経理業務に従事。企業にはトップダウン・ボトムアップ両面があるなか、三菱地所はデベロッパーという業界上、取り扱う金額が大きいため、どちらかというとトップダウンの側面が強いイメージを持っていた。
-

鬼塚 紗貴子(おにづか さきこ)
2022年 入社
ビル営業二部 副主事前職は公的金融機関でマクロ経済分析や金融機関の経営動向モニタリング業務などに携わる。三菱地所は歴史の長さからトップダウンの側面が強いのではと感じながらも、入社してからはボトムアップな面が多いことにも気づいていった。
Keyword 001「指針」
三菱地所の社員は、
ゴミを拾いながら、まちを歩く


トップダウンといえば、三菱地所が掲げるブランドスローガン「人を、想う力。街を、想う力。」が社員一人ひとりに浸透していることには驚きました。

そうそう、無理矢理覚えているのではなく、心から共感している人が多いんですよね。ちょっとした日常会話にも出てくるくらい。

愛着のある言葉ですよね。仕事に限らず、日常生活の中でも自然と「人」や「まち」の未来を思い描きながらまち歩きしていることがあります(笑)

私、入社してすごく驚いたのが、三菱地所の社員って、まちにゴミが落ちていたら必ず拾うんですよ。先輩と一緒に歩いるときに急にスッとしゃがむから、「えっ?」と思ったら、誰かが落としたゴミを拾っていた。それはまさに「人を、想う力。街を、想う力。」が浸透しているからこそで、「自分たちがまちをつくるんだ」という気持ちの体現の一つなんだなと。

まちづくりの会社として、まちをより魅力的にしたいという想いが人一倍強いですよね。

ブランドスローガンって、その言葉だけだと漠然としてしまうところもあるけど、三菱地所では個人が行動できるよう、節目ごとに上司から発信がある。例えば私の部では、共有したい価値観の一つとして、まず日々一番近くにいる、一緒に働く仲間を大切にしようと伝えられています。その想いは職場、エリア、まちへと広がっていくから、と。こうやってボトムからも指針を理解して、浸透させていることを実感しましたね。

社員一人ひとりがブランドスローガンに共感しているからこそ、ひとたび事業戦略が策定された後には、それを実現するべく各部門が一致団結しますよね。もちろん一筋縄ではいかないこともあるのですが、全員が力を合わせて課題を乗り越え、なんとしてもやり遂げる強さこそが、三菱地所の底力なのかなと感じています。

それに、策定された事業戦略が腹落ちしないときは、上司・部下関係なくフラットな関係性のもとで対話を重ねる等して、納得できるまで向き合いますよね。トップから言われたことにただ従うのではなく、社員一人ひとりが自分ごととして捉えているから、強く一致団結できるのかも。
Keyword 002「裁量」
数億円規模の契約案件も、
いきなりお任せ!?


私にとって、実際の業務面は思いのほかボトムアップでした。数億、数十億円規模の契約案件でも、まず素案は上司ではなく、現場に一番近い人が考える機会が多いです。それをベースに上司とラリーをして、できたものをもって役員に相談する。基本はそんな形で社内の合意形成が進んでいきます。

部署として最大の力を発揮するために、そうなっているのかもしれませんね。現場の考え、マネジメントの考え、それらをミックスして、チームで最適解を出していく。

これって過程を共有しながら業務を進められるから、結果として効率的なんですよね。レイヤーの間で大きな出戻りがなくて済む。上司や役員との関係もフラットで、普段あちらから気さくに声をかけてくれるので、私たちからも気兼ねなく相談できる。上下関係なく、意見もしっかり言い合いますし。

このフラットな環境、すごく新鮮でした。役員含めてランチをすることもある等、社内の距離が本当に近いですよね。仕事上では、現場の裁量は大きいながらも、判断に迷う場面では気軽に上司に相談できる空気感もあるので、心理的安全性を感じながら、精一杯目の前の仕事に挑戦できていると思います。

そう、やってみた結果、どうしてもうまくいかないことってあるじゃないですか。でも後からそれに対して現場だけが責められることはまずない。

チームで出した最適解だから、チームで次を考えようっていうスタンスですね。

上司からは、「自分(上司)をツールとしてうまく使え」ってよく言われています。
やっぱり、いざというときに上司がいてくれる安心感は大きいですよね。
Keyword 003「情報共有」
一つの繋がりが、
次の繋がりをつくる



ボトムアップってキャリア入社にとっては0から何とかしなきゃいけないっていう大変な面もあると思うんですよ。その点で三菱地所はボトムでの横の繋がりがすごく盛ん。知りたいことがあると大抵誰かが答えてくれたり、詳しい人を紹介してくれたり。

同感です。社内に「その道の専門家」みたいな方が多くいらっしゃるんですよね。デベロッパー事業は用地取得、開発、運営、売却等様々な事業フェーズがありますが、各フェーズに専門家が揃っているので、社内で声を上げれば必ず誰かの知恵を借りて課題解決できますよね。

そうそう、担当する業務以外でも、ビジネスモデル革新に繋がる取り組みであれば10%の時間を当てられる「10%ルール」という社内制度があると思うんですけど、最近はこのルールを利用して、何か新事業を立ち上げられたら面白いなって考えています。例えば、昨年はサステナビリティに関する研修を受けたので、ここで学んだアップサイクルの考え方を活かしつつ、丸の内の特産品になるようなものをつくれないかな……とか。ジャストアイディアで周囲の人に相談を持ち掛けたときは、「次はこの人に相談してみたら?」と紹介をいただいたりして、気がつけばサステナビリティに関わる方、商業に関わる方、地方創生に関わる方と、社内でどんどんつながりが広がっていってるんです。

面白そう!

うまくいくかはわかりませんけど、必ず経験になるので、絶好の学びの機会として楽しんでいます。

そのエピソード、すごく三菱地所らしいですね。「こんなことしてみたい!」という想いが人を繋いで、その繋がりから新たな挑戦が生まれていく。そんな挑戦の積み重ねが、三菱地所の成長の源泉となっているのかも。
Final Answer
三菱地所のリアルとは
両輪があってこそ、
うまく回る



三菱地所はトップダウンなのかボトムアップなのか。結論はやっぱり「両方ある」になるかな。

完全に同意見です。

トップダウンもボトムアップも、どちらもうまく機能して、うまく歯車が回っている。あらためて、それが三菱地所なんだと思いました。

本当に。どちらか一方だけだと歯車が合わないこともあると思うんですけど、もう一方の仕組みもあるから、安心して歯車を回せるっていう環境。まさに両輪として機能しているんですね。